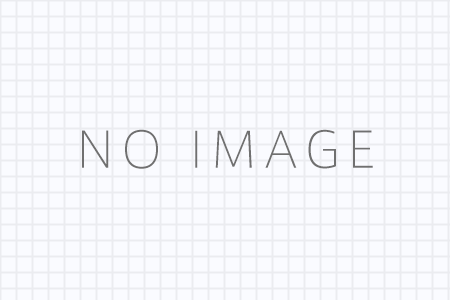はじめに
2011年9月1日歌舞伎町でビル火災。死者44名。
これは、今年9月に刊行された『セックスワーク・スタディーズ:当事者視点で考える性と労働』(SWASH編・日本評論社)の巻末付録「日本の性風俗年表」に記された21文字の史実です。本文より前に年表に目を通した私はしかし、この出来事を特に感想もなく読み流しました。
44人も亡くなってしまったのか。それは大変だったね。他にもいろんな出来事があったんだな。年表にまとまってるとわかりやすいよね。さて、本文を読み始めるか——そんな具合に。
1. 「セックスワーク=労働」までの案内図
本書はまず、セックスワークを明確に「労働」だと宣言することからスタートしていました。ここから231ページにわたり読者は、この宣言を信じるに至る丁寧で慎重な道案内を各論者によって受けることになります。論者の専門分野は多岐にわたり、性暴力サバイバー運動、エイズ運動、アート、性科学、LGBTQ運動、児童自立支援など、重なり合いながらも広範にわたる多様な視点から、運動史、社会理論、活動報告、法哲学、比較法学、オートエスノグラフィーとさまざまな枠組み・形式でセックスワークを論じています。
セックスワークを労働とみなさない考え方や、正しい性のあり方から外れたもの、取り締まられるべきものとする考え方などがいかにセックスワーカーを追い詰めてきたのかについて歴史を振り返るとともに、本書は、現在ワーカーが抱える問題の解決に何が必要とされているかも示しています。その膨大な情報量と緻密な議論はさながら、セックスワークを特別なもののように語りたい欲望を持つ読者が「セックスワーク=労働」という認識に迷わず進めるよう描かれた、手の込んだ案内図のようです。数年後あるいは十数年後に本書を手に取った人々が「こんな当然のことを、ここまで言葉を尽くさないと理解されなかった時代があったんだ」と驚く、そんな未来を信じさせてくれる本でした。
以下では、そうして言葉を尽くされた各章が、本書の中でそれぞれどのような役割を担っているか整理しながら紹介したいと思います。
2. 各章の役割と意義
第0章「セックスワークという言葉を獲得するまで:1990年代当事者活動のスケッチ」でははじめに、セックスワークを労働と位置づける議論がどう始まり、どのように世界的な広がりを見せたのかについて概観しています。さらに日本における当事者運動が国際的なつながりとまさに隣にいる身近な人とのつながりを両輪とし草の根的に生まれた歴史を、自身の経験を交えて筆者ブブ・ド・ラ・マドレーヌの視点から紐解きます。
2-1. 第1部
第1章から第4章までの第1部「社会の中のセックスワーク」では、社会がセックスワークに向けているまなざしがワーカーにどのような負担を強いてきたかを明らかにします。
要友紀子による第1章「誰が問いを立てるのか:セックスワーク問題のリテラシー」では、反貧困運動や女性解放運動などにおいてセックスワークが語られる際の典型的な枠組みを批判的に取り上げ、それらがいかにワーカーへの差別を温存し強化しているか解説しています。一方で、社会的・経済的有用性を強調することでセックスワークを擁護する議論の危険性も指摘しており、目的が何であれ社会を論じる材料としてセックスワークを「二次利用」することに警鐘を鳴らします。
第2章「セックスワーカーとは誰のことか:社会の想定からこぼれるワーカーたち」では、性暴力被害やDVの相談支援に携わってきた宇佐美翔子が、その経験を通して感じてきた相談員の「想定の狭さと知識不足」について、いかにそれが当事者の「SOSを遠ざけ」てしまうか解説しています。元セックスワーカーであることを相談現場の仲間たちに伝えるようになった宇佐美は「私にとっても賭けでしたが、それを言わなければ、セックスワーカーたちはずっと二次加害やお門違いなアドバイスをされ続けると思いましたし、元セックスワーカーだと相談員である私自身が告白できないなら、そこは安全に相談できる場所ではないということでもあったのです」と現場を振り返り、相談支援等に携わる読者に対して、積極的に知識をつけること、相談者に自分の「普通」の概念を押し付けないこと、そして多様な相談内容に対応する意思を自ら表明することで相談しやすい環境を作ることを求めています。
山田創平による第3章「なぜ『性』は語りにくいのか:近代の成り立ちとセックスワーク」では、近代的な家族概念と「正しいセクシュアリティ」という性道徳・性規範の成り立ちが解説されます。さらにこの近代的な性のヒエラルキーにおいて、セックスワークがLGBTQ+やシングル親、非嫡出子など他の問題と地続きの問題であることを説得的に明確にしています。
松沢呉一による第4章「法規制は誰のためにあるのか:セックスワークをめぐる法の歴史と現在」は、性に関する法的取り締まりの歴史的変遷を読み解きながら、女性を守るという名目で実施された法的試みがいかに性道徳観念に基づく差別的なものだったか、また結果としてどのようにワーカーを不利な状況に追い込んできたかを明らかにします。
戦後史を別の側面から概観しているのが、畑野とまとによるコラム「トランスジェンダーとセックスワーク」です。畑野は「近代のトランスジェンダーの歴史は、まさにセックスワークの歴史であ」るとし、「トランスジェンダーとしても、またセックスワーカーとしても人権が尊重され、差別的な扱いを受けない社会にならなければ」ならないと結論づけています。
2-2. 第2部
第2部「セックスワーカーの権利を守るには」では、セックスワークをめぐって現在世界で起きているさまざまな議論や運動の概要をつかむことができます。
東優子による第5章「性の健康と権利とは何か:権利主体としてのセックスワーカー」では、しばしば道徳や自己責任、規制や犯罪という文脈で語られる性の健康の問題が、女性の自己決定権などのジェンダーの視点や公衆衛生問題としてのエイズ・パンデミックの教訓を通して、国際機関や人権団体によって明確に人権問題と認識されるようになった過去数十年の流れを概説し、性の健康に関する議論に歴史的文脈を与えています。
第6章「セックスワーカーへの暴力をどう防ぐか:各国の法体系と当事者中心のアプローチ」で青山薫は、当事者中心の観点から(犯罪化や合法化ではなく)非犯罪化アプローチが採用される理由を解説した上で、ポスト植民地主義フェミニズム、第三世界フェミニズム、世界システム論フェミニズムなどを背景に生まれたセックスワーカー権利運動がどのように世界各地域で発展し、その蓄積が影響力を得てきたかを概説します。この運動が当事者中心主義を一貫してきたこと、人身取引問題を深刻視しながらも移住労働者としての移動や職業選択の権利を主張してきたこと、調査研究や政策提言などを実施し国際機関や人権団体に影響力を持ってきたことを概観し、さらに当事者が主体となって実施する学術的な協働プロジェクトの新たな試みを紹介しています。
翻って日本における調査研究のひとつとして、第7章「どうすれば安全に働けるか:セックスワーカーの労働相談と犯罪被害」で要友紀子は、電話相談事業を通して見えたワーカーの困難の原因が、セックスワーク自体ではなく、困難の発生の蓋然性を高める社会的・法的・政策的な条件であることを明らかにします。
当事者運動としてさらに、篠原久作がコラム「ウリ専経営者から見える業界の今とこれから」で自身のウリ専(ゲイ・バイセクシュアル男性向け風俗)ワーカー・マネージャーとしての経験を振り返り、ピアサポートのひとつのかたちを示しつつ、近年ウリ専のあり方が急速に変化していると指摘します。
2-3. 第3部
ここまでの議論を踏まえ、第3部「セックスワーカーとの関わりかた」では、ワーカーを支援したり、表現や議論においてワーカーを取り上げる際に注意すべきことが解説されています。
第8章「合意とは何か:性が暴力となるとき」で岡田実穂は、ワーカーを「被害者」と一面的に解釈することで「セックスワーカーは合意できる主体ではない」と決めつけることの暴力性を批判しながら、一方で、現行の法律とその運用において性経験の少なくない者——特にセックスワーカー——に対し「セックスに合意していただろう」とする差別的偏見があることを批判し、セックスに関する合意形成プロセスの単純な理解に警鐘を鳴らします。
自らも表現者としてアートに携わるげいまきまきが第9章「当事者とどう向き合うか:セックスワーカーと表現」で語るのは、2014年と2016年に起きた表現者によるワーカーの人権軽視の事例です。これらをげいまきまきは「当事者不在の表現」と呼び、当事者が企画制作等に参加していないこと、当事者の表層的イメージを利用するものであることを指摘します。さらに当事者に向き合ったアート作品の例も紹介し、表現の結果を引き受ける——責任を持つ——とはどういうことかを検討しています。
宮田りりぃによる第10章「セックスワーカーにどう併走するか:当事者による経験の意味づけ」は、あるワーカーが当事者運動に出会い、セックスワークを「専門性をもつ仕事」ととらえるようになるまで道のりを紹介し、その上で、いかにスティグマ(負の烙印)やスティグマに基づく周囲の言動がワーカーの信頼的な人間関係の構築維持や適切な知識と性の健康へのアクセスを阻害しているかを論じ、改善のために何が必要かを検討しています。
本書を締めくくるコラム「児童自立支援施設からの報告」で筆者あかたちかこは、子どもたちがセックスワークに関わった理由と背景の複雑さと多様さを指摘します。そしてそれを大人の道徳観でジャッジするのではなく、耳を傾け、細かく柔軟な対応を心がけることがいかに大切か説明しています。
3. 当事者中心の実践としての本書
本書の意義は、大きく次の三点と考えます。
ひとつめは、あらゆる専門性やバックグラウンドを駆使して網羅的な議論をしていることです。読者が全ての章を説得的だと思わなかったとしても、どこかにセックスワーク=労働という考え方を理解する糸口が何かしら見つかることでしょう。それは女性の自己決定権かもしれませんし、移住労働、近代社会の資本主義と家父長制、性暴力被害者支援、国際的なフェミニストの連帯、アート創作かもしれません。
ふたつめの意義は、各論者が、社会はこうあるべきだという社会正義/社会設計の観点や、女は/セックスワーカーは/トランスジェンダーは/同性愛者は/貧困者は/etc.こうあるべきだというパターナリズムの観点を徹底的に排除していることです。ワーカーひとりひとりを既に社会に生きている主体ととらえ、奪われているかれらの尊厳と権利の回復のために言葉を尽くしているのです。
そして最後に、論者の多くがセックスワークの経験を持つ当事者の立場性を有していることです。これまでにもセックスワークについて語られた書籍や論文はありました。論者自身がワーカーとして参与観察したものもありますが、しかし全体を見ればセックスワーカー自身による論考や調査は非常に稀です。当事者主体の権利運動を語るにあたり当然のこととはいえ、本書のような執筆陣を揃えたことは(悲しいかな)画期的なことと言えるでしょう。
4. 顔のあるセックスワーカー
本書の末尾には、用語解説と「日本の性風俗年表」が収録されています。本文を読み終え、改めて年表を開いた私は、そこに書かれたひとつひとつの出来事をもう以前のように読み流すことができませんでした。
2011年 9月1日 歌舞伎町でビル火災。死者44名。
たとえば、冒頭で紹介したこの火災。麻雀店のある3階では19名中16名が死亡、4階のセクキャバでは28名の全員が死亡しました。
これをしかし読者は、もう44とか16とか28という数字で読むことができません。ワーカーひとりひとりに顔があり、生活があり、権利が、尊厳が、意志が、自由が、そして主体性があることを、231ページかけて既に知ってしまっているのですから。