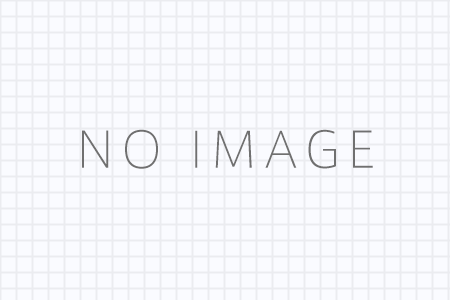前回に引き続き、トランスジェンダーの話題に触れたい。
ツイッターを芋づる式にいろいろ見ていたら、「ジェンダーが無くなれば、トランスジェンダーというあり方も無くなる」という意見が目に入ってきたからだ。いわく、ジェンダーの解体こそが目指されるべきなのだから、トランス女性やトランス男性のようにジェンダーというシステムに裏付けされた女性性や男性性という概念を前提とする存在はジェンダーの解体に逆行していて問題だ、という主張だ。
これに同調する別の人のツイートには「性別による差別があり、それをジェンダーと呼んでいるのだ」とあった。
まず「ジェンダー」が何を意味しているのか、私の解釈——社会学やカルチュラル・スタディーズ、女性学、哲学などの分野ではある程度支持されている解釈だと私が思うもの(※)——を手短に説明したい。
※ここで学問を持ち出すのは、学術的な権威によって正しさが保証されると思っているからではありません。念のために、ここで紹介する「私の解釈」は私個人だけの独特な考え方というわけではなく、「ジェンダー」という言葉を使って社会を語る人々のうち多くの人が採用している解釈です、という補足情報として書きました。
ジェンダーとは何か
セックスが生物学的性別で、ジェンダーは社会文化的性別だ、という説明を耳にしたことがある人は多いだろう。しかしこれは「ジェンダー研究入門編」で語られるようなことであって、その説明を鵜呑みにしたまま「ジェンダー研究応用編」に進んでしまうと混乱することになる。
では「応用編」でジェンダーはどのように解釈されているのか。
ジェンダーとは、人類をある特定の身体の特徴群(主に内外性器と生殖器官)に注目して二つに分類する解釈の枠組みだ。人間の身体にはさまざまな部位があり、その部位ひとつひとつは人それぞれとても多様だ。たとえば爪の形、耳たぶの厚さ、歯並び、胃の大きさ、視力、その他いくらでも例が挙げられる。それら無数の部位のうち内外性器および生殖器官に当たるいくつもの部位をひとまとめにして、その特徴をたったの二つに分け、それによって人類を男と女という二つの種類に分けているのが、ジェンダーという枠組みだ。
ジェンダーは解釈の枠組みだが、その枠組みは、服装や振る舞いなどのジェンダー・エクスプレッション gender expression(ジェンダー表現)、職業や家庭内分業などのジェンダー・ロール gender roles(ジェンダー役割)などによって支えられている。
ジェンダー表現やジェンダー役割によって、私たちは日常生活において他者や自身の特定の身体の特徴群を確認するまでもなく(例えば自分の染色体を調べたことがある人はあまりいない)間接的に身体の特徴群を予測できるようになっている。実際は子宮を持つことと育児をすることは必然的な繋がりを持っていないし、陰茎を持つことと世帯主になることは必然的な繋がりを持っていない。にもかかわらず、私たちにはジェンダー・ステレオタイプ gender stereotypes(ジェンダー偏見)が刷り込まれていて、ジェンダー表現やジェンダー役割が特定の身体の特徴群の現れであると信じ込むように仕向けられている。
ジェンダーという枠組みは、このように「分類の根拠としての身体があって、分類の結果物としてのジェンダー表現やジェンダー役割がある」という見せかけを身にまとっている。これは先に書いた「セックスが生物学的性別で、ジェンダーは社会文化的性別だ」という考え方と相性が良い。
しかし実際に日常生活において私たちは、内外性器や生殖器官、もっと言えば染色体やホルモンの状態など、身体の特徴群を直接確認しあってはいない。分類の根拠であったはずのものは、結果物からさかのぼって類推されるものになっている(※)。
そう考えると、ジェンダーという解釈の枠組みが私たちの日常生活において機能しているのは、実際の身体の特徴群の現れというより、むしろジェンダー表現やジェンダー役割、そしてそれらを身体の特徴群の現れであると信じ込むように仕向けているジェンダー偏見による働きだ。分類の結果物であったはずのものがひとり歩きをしており、あたかも、結果物が同時に根拠として機能し、それがまた結果物を生み出す、自己循環のシステムのようだ。
そうやってジェンダーという枠組みは繰り返し繰り返し反復され、固定化される。ジェンダーが反復の繰り返しと言われるのは、単純に言えばそういう話だ。そして、解釈の枠組みとしてのジェンダーがこういったプロセスで自己を維持、正当/正統化していることを指して、ジェンダーはシステムだ、と言われることもある。
※これは、内外性器や生殖器官、染色体、ホルモンの状態などが存在しないとか、無視していいという主張ではありません。当然のことですが、例えば前立腺を持たない人は前立腺ガンにはならないし、子宮を持たない人は子宮ガンにはなりません。ここではそういった、必要に応じて単一の部位に注目する時の話ではなく、複数の身体部位の特徴群をひとまとめにして「人には男というものと女というものがあり、両者には大きな隔たりがある」と解釈する枠組み、つまりジェンダーのことを話しています。
差別なきジェンダーは存在し得るのか
冒頭で「性別による差別があり、それをジェンダーと呼んでいるのだ」という解釈を紹介したが、ジェンダーは単なる解釈の枠組みでしかない。ジェンダーが差別である必然性は無いのだ。
ジェンダー表現やジェンダー役割に、人々を実際に今苦しめているものがたくさんあるのは事実だ。しかしそれはジェンダーがあるから苦しいのではなく、賞罰——望ましいとされるジェンダー表現をすれば承認され、しなければ否定される、あるいは望ましいとされるジェンダー役割を担えば承認され、しなければ否定されるという状況——があるから苦しいのだ。
例えば「県民性」という概念がある。〇〇(都道府県名)の人々はこんな性格で、こんな食べ物を好んでいて……という考え方のことだ。日常会話でもこういった話は時々出てくるし、テレビでも「県民性」をメインに取り上げる番組は人気だ。
一見問題ありそうだし、不愉快な感情を持つことはあるけれど、私は(沖縄を除いて)「県民性」を差別問題としては認識していない。そもそも「県民性」など(沖縄を除いて)本気で信用している人はわずかだ。偏見が外れていれば「何だよ普通かよw」と笑いが生まれるし、偏見が本当なら「本当なんかよw」と笑いが生まれる。その程度の与太話でしかない。偏見通りに生きたところで大きなメリットもないし、偏見に抗って生きたところで大きな不利益もない。(沖縄を除いて)特定の都道府県の出身であることが不利益になるような社会構造も無い。(※)
つまり、「県民性」はジェンダーと同じく人の分類の枠組みであり、偏見も存在しているにもかかわらず、(沖縄を除いて)社会全体としてそれが差別的に機能しているということはない(個人的に例外を経験することはあるかもしれないけれど)。
※「県民性」という都道府県の話なので例外は基地問題を押し付けられていてかつ牧歌的なイメージを押し付けられている沖縄だけだと思いますが(違ったらごめんなさい)、もっと小さな地域単位に視点を移すと、部落差別、外国人コミュニティなど地域を基にした差別は存在しています。
@nekura_san4さんより、私が沖縄の問題を民族差別だと気づいていないとのご指摘を受けました。ご説明を求めたところ、私の書き方が不十分だった故の誤解があったようです。改めてこちらに明言しておきますが、私がここで「(沖縄を除いて)」と繰り返しているのは、沖縄には植民地主義や民族差別や迫害の歴史があるから他の地域と同列に語ることはできない、と考えているからです。
ジェンダーも、そのレベルにまで落とすことは可能だと思っている。
実際私たちは、フェミニズム運動を中心に、ジェンダーのシステムの反復の繰り返しに介入してきた。「そうじゃない女もいる」とか「新しい女性像はこれだ」とか「女にそれを押し付けるな」とか、やり方はさまざまだし、相互に矛盾することはあっても、「女とは〇〇だ」というジェンダー偏見を塗り替えてきた。
例えば「県民性」のような(沖縄を除いて)社会全体として差別的に機能しているわけではないレベルを超えて、一切の偏見が無い状態を目指すとなると、それは確かにジェンダーが無くなることを目指すのと同義だろう。それこそ耳たぶの厚さなどの、人類を分類する目的では誰も注目していないようなことと同レベルにまで落とすということなのだから、そうなれば誰もジェンダーについて普段語ることも、表現することもしなくなる。
しかしそれは途方も無いプロジェクトだ。現実的には、偏見を塗り替えることでジェンダー表現やジェンダー役割の内容を変えていき、「女」のそれと「男」のそれの差異を狭めていきながら、自由を増やしていくという道しかない。反復の繰り返しに介入し続けるしかないのだ。その先には、もしかしたらジェンダーが無くなるという事態が待っているのかもしれないけれども。
それまで私たちはどう生きればいいのか、どう生きてよいのか
そのプロセスの中で、私たちは生きていかなければならない。今生きている世代はきっと、ジェンダーが無くなる事態どころか、差別なきジェンダーにすら到達できないまま人生を終えるだろう。
冒頭で「ジェンダーが無くなれば、トランスジェンダーというあり方も無くなる」という意見を紹介した。ジェンダーの解体こそが目指されるべきなのだから、トランス女性やトランス男性のようにジェンダーというシステムに裏付けされた女性性や男性性という概念を前提とする存在はジェンダーの解体に逆行していて問題だ、という主張だ。
上で書いた通り、私たちはほぼ全員が、ジェンダーという枠組みを刷り込まれている。人を男女に分けて見る目線を内面化している。ジェンダー表現をしたりそれに抗ったり、ジェンダー役割を担ったりそれに抗ったりしながら、ジェンダー偏見を強化したり変容させたりしている。私たちは真に「女でもなく男でもないあり方」がどんなものなのか想像することしかできない。そのくらいにジェンダーのシステムは私たちの生活の隅々にまで張り巡らされている。
だから、トランスジェンダーの人々のうち「男性」というアイデンティティや「女性」というアイデンティティを持っている人のそのアイデンティティが社会的に構築されたジェンダーという枠組みに乗っかっているという指摘は、確かに正しい。その枠組みの存在があるからこそ、性別のアイデンティティが存在できるのだから。
けれどそれは、シスジェンダーの人々も同じなのだ。望ましいとされるジェンダー表現やジェンダー役割を積極的に引き受けている人はもちろんのこと、そうではなく抗っている人たちだって、その枠組みの外側にいるわけではない。押し付けられるジェンダー表現やジェンダー役割をどんなに不当だと感じていたとしても、自分が振り分けられた側の性別それ自体に強い違和感を感じたり嫌悪感を感じてはいないシスジェンダーの人々も、やはりジェンダーという枠組みに自己のあり方が乗っかっているのだ。
さらに言えば、シス/トランスにかかわらず、異性愛者も同性愛者も両性愛者も、ジェンダーという枠組みの中でしか存在できない。私たちのほとんど全員の性的欲望や恋愛感情は、ジェンダーという枠組みの中で構築されている。
ジェンダーが無くなる事態や差別なきジェンダーの実現を待っているあいだ、それらを望む私たちは、ジェンダーという枠組みに依拠するような——そしてジェンダーのシステムの反復の繰り返しに貢献するような——あり方を一切やめなければいけないのだろうか。そんなふうに生きることが、はたして可能なのだろうか。
例えば、婚姻制度から除外されている同性愛者や、高校無償化制度から除外されている朝鮮学校の生徒がいる。かれら(※)の中にはそういった差別的取扱いに抗議し、制度の適用を求める人々がいる。しかし、そもそも婚姻は家族制度、戸籍制度、移民制度、税法、社会保障制度など広範にわたる問題群の交差点だし、そもそも少数民族の民族教育の権利を国が保障していないことや、高校が実質義務教育化しており高卒が学歴の最低基準となっていることは無償化どうのこうのよりも根本的な問題だ。
それでも私たちの多くは「そんな小さな権利を求めるのではなく、制度の解体を目指すべきだ、そうでないならお前たちは現状維持を求める差別主義者だ」と言うのだろうか。
※私は「かれら」というひらがな表記を、性別を指定しない三人称複数の代名詞として使っています。
以前このブログで以下のように書いた。
家族の中、地域の中、友人関係の中で結婚と離婚を何度も見てきた私は、人々が様々な理由で結婚を選ぶということ、そして彼ら彼女らの頭の中では膨大な量のリスク管理が行われていることを実感を持って知っている。そして多くの人にとっては、結婚にはそれなりの「必要性」「メリット」「意義」があるのだし、それは Mary Bernstein が記事中引用で言っているような「(結婚したいと思う人は)外部からの承認を求めている」というだけのことではなく、もっと複雑なことなのだ。
「永遠の愛を誓いません」と言える特権
婚姻制度は、出入国管理や医療保険制度、社会保障制度などなど他の社会制度との共犯関係において、結婚することの「必要性」「メリット」「意義」を作り出すために存在している。結婚とは、政府主導のもとマイノリティーを対象として売り出されているパッケージ商品であり、それは政府の他の制度の欠陥や失敗を覆い隠し、維持し、それらの欠陥制度の根本的変革(それには大層お金がかかる)を阻止する機能を持っている。
(中略)
要するに、もろもろの社会制度によって重層的に疎外・周縁化(「普通ではない」とされて異端視されたり権利を奪われたりすること)されている度合いが高ければ高いほど、その人は結婚に「意義」を見出しやすくなるだろう。婚姻制度においては、最も特権を持っているのは既婚者でも異性愛者でもなく、結婚しても離婚しても特に大きなメリットもデメリットもなく、よって好きな時に結婚も離婚も選択できる人たちである。
制度を利用することにメリットがあり、利用しないことにデメリットがあるような賞罰の存在がある時——しかもそのメリットやデメリットが、マイノリティーであるがゆえに余計に大きくなっている構造がある時——私たちは、等しく人生を歩んでいる他者がその制度を利用した時に「お前は間違っている」と非難できるだろうか。ましてや、私たちがそのような制度を利用することも利用しないことも選べるような特権的立場にいる時、ある特定の人々にだけそれを利用してはいけない、利用するならお前は差別者だと非難することは、正しくないのではないか。
結婚してもしなくても別にどっちでもいいや、高校が無償になろうが自分には影響ないし、高校に行かなくても生きていける財産がうちにはあるから別にどうでもいいや、「女」に押し付けられるジェンダー表現やジェンダー役割は自分で取捨選択して、不当なものは拒否すればいいや、というのは、特権的な立場だ。生きているあいだに少しでも自分の人生をマシにしようと漸進的な変化を求めている人々を尻目に「そんなちゃちい変化、要らないよ」と言えるのは、特権的なことなのだ。
逸脱を許されないトランスジェンダーの人々
トランスジェンダーに話を戻すと、トランスジェンダーの人々はジェンダーという枠組みのダブルバインドに苦しめられることが多い。例えばトランス女性があまり女性的でないとされるジェンダー表現やジェンダー役割を身にまとっていると「偽物だ」「女性とは言えない」「ただの女装ではないか」「あんなのまで女だと言うのか」などと愚弄されるが、翻って女性的とされるジェンダー表現やジェンダー役割を身にまとっていると「ジェンダー偏見を強化している」「差別を肯定している」「それが女だというお前の偏見だろう」「存在自体が問題だ」などと非難される。現在トランス女性が特にこういった目に遭いやすいだけで、実際個人レベルではトランス男性にも似たようなダブルバインドに苦しめられている人はいるだろう。
シスジェンダーである特権のひとつは、ある程度の範囲内であればジェンダー偏見から逸脱しても大丈夫であることだ(※)。「ある程度」がどのくらいを指すのかは場面場面で異なるだろうし、逸脱を認知的に処理するために周囲が「料理が好きだなんて、やっぱり女の子だね」などと余計なことを言ってジェンダー偏見の温存を試みることはあるけれど、存在自体を否定すべきものだとされたり、アイデンティティを疑問視されたりといった経験は、圧倒的にシスジェンダーの人々よりもトランスジェンダーの人々に多い。だから当然トランスジェンダーの人々は、ジェンダー表現やジェンダー役割をある程度引き受けるという選択をすることが多い。
※圧倒的にシスジェンダー男性の方がシスジェンダー女性よりも逸脱を許されているというアンバランスさも指摘しておきたい。
一方、先日このブログで以下のようにも書いた。
性別についても、先日トランス男性が「性別移行をしてから、自分にとっての男性性って何だろうって思うようになった。それまで目指してきた男らしさというのが、ある時から窮屈な規範に感じられるようになった」と話していた。
「トランスコリアン」が安易な3つの理由と1つの原因
これは男女問わず他のトランス当事者からも聞いたことのある葛藤だ。自分が目指している女性性はミソジニーを含んだジェンダー規範に則ったものなのではないか、というトランス女性の葛藤も耳にすることがある。
トランスジェンダーの人々は、皆が何も考えずにジェンダー偏見に乗っかっているわけではない。シスジェンダーの人々の中にジェンダー偏見に苦しんでいたり抗おうとしている人たちがいるのと同じように、トランスジェンダーの人々にもジェンダー偏見に苦しんでいたり抗っている人たちがいる。
当然のことだ。ジェンダー偏見によって押し付けられるジェンダー表現やジェンダー役割をすべて好ましいものと思うかどうかと、自分がそのジェンダーにアイデンティティを持つかどうかは、関係のないことなのだから。
いわゆる「TERF」(トランス排除的ラディカル・フェミニスト)の中には「スカートを履きたい男性として生きればいいのに、どうして自分は女性だと主張するのか」と疑問視する人がいるが、その視点自体は正しい。スカートを履きたいと思うことと自分を女性だと思うことは、本来全く関係のないことだ。
実際、スカートが好きなトランス女性もいれば、スカートが嫌いなトランス女性もたくさんいる。当然スカートが嫌いなシスジェンダー女性がいるのと同じだ。彼女らの違いは、スカートを履かないと——スカートに限らず、化粧をしないと、ニコニコしていないと、男性を立てないと、高い声で話さないと……——女性であるという自分のアイデンティティすら猛烈に疑われてしまうだろうという恐怖があるかどうかだ。
性別移行(トランジション)の初期にはがっつり女性に押し付けられているジェンダー表現やジェンダー役割を身にまとっていた人が、移行が進むにつれてそれを脱げるようになるというのも、そういう背景があるからだ。シスジェンダー女性がそれまで押し付けられてきたジェンダー表現やジェンダー役割を降りることは「脱コル」と呼ばれているらしい。コルセットを脱ぐ、という意味だ。
実は、トランス女性にも脱コルをしている人は多い。トランス女性が自分のアイデンティティに沿った生き方をするためには、一度コルセットを着るプロセスが必要になっているというだけの違いだ。
そしてその「一度コルセットを着る」というプロセスは、ジェンダー表現やジェンダー役割としては、必要にかられて婚姻制度を利用したり、利用する権利を求めたり、高校無償化の恩恵を受けたり、恩恵を受ける権利を求めることと同じだ。より大きな問題をひとまず横において、今ある制度の中で生きようとしている人々の行動なのだ。
また、一度コルセットを着てでも自分のアイデンティティに沿った生き方をしたいと望む内的な感情としての側面は、異性愛や同性愛や両性愛の欲望や感情を持つことと同じだ。ほかの全ての人と同じように、刷り込まれたジェンダーという枠組みに依拠した欲望や感情やアイデンティティを持っているだけのことだ。
トランス女性にだけその責任を強く問うこと——ましてや「存在自体が問題だ」とまで罵倒すること——は、端的に言って、不当なことだと思う。
シスジェンダーの異性愛男性ばかりが得をする制度
現行のジェンダーのシステムは、シスジェンダー男性——特に異性愛男性——を特別に有利にしている。男性に対してもジェンダー偏見はあるが、女性が押し付けられているそれの比ではないし、偏見のとおりに振る舞えば日常生活で大きく有利に働くし、逆にそこから逸脱した時のデメリットも女性に比べて小さい。偏見の内容だけでなく、賞罰のあり方も圧倒的にシスジェンダーの異性愛男性に優しいのが現行のジェンダーのシステムだ。
その点では、私はほぼシスジェンダー男性であるから、異性愛者ではないとはいえ、ジェンダーのシステムを利用することを肯定する意見を公に書くのは、そのシステム自体を肯定することになりかねない。トランス女性が「一度コルセットを着る」ことを責められるいわれはないと書くことも、自分に有利に働いているジェンダーのシステムを温存しようとしていると解釈できるだろう。シスジェンダーの男性——特に異性愛男性——にとっては、ジェンダーのシステムを変容させることは魅力的ではなく、むしろ現状維持が一番自分に特に働くはずなのだから。
それでもやはり私は、ジェンダー表現やジェンダー役割を押し付けているジェンダー偏見を不当だと認識し、ジェンダーのシステムを変容すべきだと思っている。
そんな私や、他のシスジェンダー男性——特に異性愛男性——に求められているのは、特権をサっと手放して、差別など存在しないかのように振る舞うことではない。性別なんてないよね、どうでもいいよね、好きな服を着て、好きなことすればいいんじゃない、うちらは平等だよね、という体(てい)を取り繕うのではない。突然自分だけがシステムから自由になることはできないのだ。
そうではなく、現実に今存在しているジェンダーのシステムの中で、自分に与えられた有利性(差別問題の文脈では特権と呼ばれる)を利用して差別に対抗することが求められているのだと思う。それには経済的有利性を利用して寄付をすることや、教育の機会の有利性を利用して運動団体で目立たないが面倒な業務を引き受けることや、男性にしか聞く耳を持たない相手に語りかけることなど、色々な方法があるだろう。
逆に言えば、トランスジェンダーの人々に限らず、異性愛、同性愛、両性愛、シスジェンダーの人々がジェンダーのシステムをしばらくのあいだ利用することを肯定、あるいは少なくとも「仕方のないこと」と認識している私のようなシスジェンダー男性——特に異性愛男性——は、率先してジェンダーのシステムの変容に尽力しなければならない。ジェンダーのシステムを利用してでも。
そうでなければ、自分に有利な現状を維持することに加担してしまうのだから。