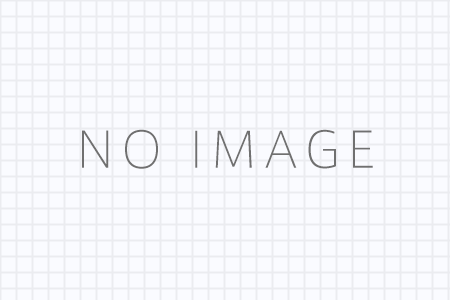R/EVOLVE-結婚と平等とピンクマネー
関西クィア映画祭 上映日時
【大阪】 9/14(土) 13:55開演 (13:35開場)
【京都】 10/5(土) オールナイト
作品紹介本文
この原稿を依頼され、どんな映画なのか調べてみると、 Lil'Snoopy Fujikawa が出演しているという。私と Lil'Snoopy との最初の出会いは、映画の舞台でもあるシアトルだった。シアトルに用事があり、友人と一緒に自宅に泊めてもらったのだ。とても明るく、でも思慮深く優しい、素敵な人である。ぜひ映画を見てみたいと思い、原稿依頼を受けることにした。本編を見てみると、Lil'Snoopy 演じるラクーンは正に Lil'Snoopy にしか演じられないような素晴らしいキャラクターで、画面に Lil'Snoopy が映るたびに映画内世界がパッと明るくなり、見ているこちらまで楽しくなってしまう。観客のみなさんにも、主人公リンカーンと一緒にラクーンとの出会いを楽しんでもらえたらと思う——
とうとう同性婚が認められるかもしれないというワシントン州。ある日リンカーンは、7年連れ添った彼氏ルーカスから結婚を申し込まれる。同性婚支援団体マリッジ・イクォリティーでボランティアをしているルーカスは、同性婚が実現すること、そしてリンカーンと結婚することを心から望んでいた。リンカーンもまた、愛し合っているだけで十分だと茶化すものの、すぐに満面の笑顔で「イエス」と答える。
しかしこの映画は、リンカーンとルーカスの愛を描いたものではない。
広告会社で写真家として雇われたリンカーンは、同性婚支持に傾く政治の流れを利用するよう大企業に企画をもちかける。その企画とは、マリッジ・イクォリティーに多額の寄付をし、都市部でのイメージアップのためにLGBTフレンドリーな企業像を打ち出そうというものだ。しかしこの企画に乗った企業が選んだモデルは、若くてルックスのいい白人男性2名だった。
しかしこの映画は、企業がどうやってLGBT市場に取り入るかを描いたものではない。
リンカーンはある日ラクーンと名乗る奇抜な格好をしたヒッチハイカーを車に乗せる。貨物列車に乗ってきたというラクーンの破天荒さに戸惑いつつも、企業のためではなく再び自分のために写真を撮りたいと思うリンカーンは、被写体としてラクーンを自分の生活に歓迎する。「同性愛者であること以外『普通』のアメリカ人」のためではなく、世界中のあらゆる差別や困難への抵抗と連帯しようとするラクーンの仲間たちと出会い、リンカーンの気持ちはルーカスとすれ違い始める。
しかしこの映画は、偏狭な主流同性愛者権利獲得運動を盲信していた主人公がマルチイシュー(複数の抑圧への抵抗を、優先順位をつけずに同時に試みるやり方)なクィア運動に目覚める成長物語ではない。
この映画は、あらゆるしがらみや義務、思い込み、策略、私欲などがなくなったところには普遍的にクィアなものがあるということを示している。ルーカスの「愛」、企業の「イメージアップ」、そして同性愛者権利獲得運動団体の「優先順位」——そういうものは、ルーカスの言葉を借りれば、「普通の人」が考えることだ。「普通の人」は「路上のクィア」の写真を企業のイメージアップに使えると思わないし、「普通の人」はヒッチハイクなんてしない。「普通の人」は川に飛び込まないし、「普通の人」は可処分所得がある。「普通の人」はゴミ収集庫から食べ物を調達しないし、「普通の人」は貨物列車じゃなくアムトラックで長距離を移動する。「普通の人」は同性とセックスなんてしないし、「普通の人」は出生届の性別に何の不満もない。——「普通の人」とは、LもGもBもTもQもそれ以外も、みんなが苦しめられてきた元凶の概念だ。
誰もが生まれたときから「普通の人」だったわけではない。わたしたちは小さいころ所構わず排泄していたし、食事中に大声でわめいて叱られた。学校に行ったふりをして公園で時間をつぶしたり、こうしろああしろと言う大人に悪態をついた。そのうちに学んできたのだ。「あぁ、従うことは、賢いことなのだ」と。そしてまた、こんな汚い知恵もつける。「従わないで痛い目にあうのは、自業自得なのだ」と。
米国でエイズパニックが起きたとき、エイズは「同性愛ガン」と呼ばれ、市民の健康の問題としてではなく、特殊なライフスタイルを望み実行する同性愛者どもの「自業自得」として、政府にも地域にも放置された。あの時、同性とセックスするということは、「やめろと言われてるのにやった」「従わなかった」ということだったのだ。なぜなら、再びルーカスの言葉を借りれば、「普通の人はそんなことしない」からだ。
つまり、ラクーンの生きている世界は特殊な「クィア」文化で、リンカーンやルーカスが生きてきたのが「普通」の文化、という構図は間違えている。ほんの20〜30年前、リンカーンの文化は特殊で、病的で、罪的で、おぞましい文化——つまり奇妙でおかしい「クィア」側に置かれていたのだ。この20〜30年で起きたことは、「クィア」文化のなかから世の中に都合のいい部分だけが取り出され、漂白され、「普通」の側のだいぶ低ランクなところにチョコンと置かれたというだけのことだ。
こうして「普通」の文化は、金や権力を持つ者たちに都合のいいように構築・再構築され続けている。であれば、特殊なのは「クィア」ではない。「普通」のほうが、よほど人工的で、不自然だ。もしわたしたちが、しがらみも義務も思い込みも策略も私欲もないところに行くことができたなら、わたしたちの生き方や考え方、物事のとらえ方や抱える思いは、きっと「クィア」なものになるだろう。
「クィア」を指さして、自分たちはあれとは違うと自分に言い聞かせ、自分たちの「普通」さに安心したい——それは理解できなくもない。いつマリッジ・イクォリティーのスタッフのように「君の仲間の化け物だろ!」と言われるかわからないのだから、怖くてしかたがないだろう。ましてやその「化け物」は、「漂白され得なかったもの」——自分たちが裏切り、「あちら側」に置きざりにしてきたもの——なのだから。
リンカーンは、その「普通」と「クィア」のあいだを揺れ動いている。「あちら側」に置きざりにしてきたものと、「こちら側」にある愛、仕事、優先順位のあいだで引き裂かれている。しかしこれは、ラクーンに会ったことで初めて感じた戸惑いではない。ラクーンは単に、思い出させてくれただけだろう。カメラで写真を撮り始めたときのリンカーンの情熱を。
そもそもリンカーンがラクーンのため車を止めたのは、性欲でも愛情でも友情でもなく、ピンク・トライアングルという連帯の象徴を見たからだった。また、過去に撮り溜めた写真には、リンカーンが本当に撮りたかったものがたくさん写っている。人種を白人に限定し、性別を男性に限定した企業とは、求める被写体に大きな違いがあった。ルーカスもまた、リンカーンの過去の写真を見て、複雑な思いを抱え始めるのだ。映画の冒頭に出てくる写真の入った封筒にも、「Queer」(クィア)の文字が書かれていた。
より「普通」になっていくことを成長——growing up——と呼ぶのなら、この映画はむしろ、その逆——growing down——を描いた物語ということになるだろう。森を探索したり、着たら怒られるような服を着たり、ペンキを手に付けて遊んだり、川に飛び込んだり、靴を履いたままダッシュボードに足を乗せたり、壇上で人が話しているのに大きな声を出したり……ラクーンの影響で、リンカーンはどんどん子どものようになっていく。自由になる金もなく、ありあわせのもので工作したり、義務だからではなく楽しみながら何かをしたり、人の目を意識せずに絵を描くような、そういう子どもになっていく。
そして「子ども」は、大人より少しだけ、クィアだ。
「男の子なのにスカートなんか履いて」いたあの頃、「女の子なのにそんな乱暴な遊びをして」いたあの頃、「女の子なのに食器のひとつも片付けやしな」かったあの頃、「男の子同士で気持ち悪く手なんかつないで」いたあの頃——わたしたちは、あの頃、クィアだった。ある程度の分別を教えこまれて、レストランで大声を出さなくなったあの頃だって、そこそこのクィアだったのだ。
この映画が教えてくれるのは、もちろんそれだけではない。社会運動に携わる者にとっては、いくつもの教訓が込められている。
政治家と企業がLGBTフレンドリーな素振りを見せたら、まず疑ってかかること(たとえば日本維新の会が同性婚を支持している事実をどう受け止めるのか)。
自分の所属する団体が莫大な資金を必要としているとしたら、そこにそれだけのお金をかける必要があるのかを再度問うこと(「使われてる」ボランティアが多い団体も注意が必要だ)。また、それだけのお金をかけるために、大切なものを裏切っていないか確認すること。
手作りで、あるいは低予算でできる活動だからこそ可能なことがあるのかもしれないということ(「あなたは美しい」と日本語で書いた紙を車のワイパーに挟んでおいたら、ストーカー被害だと思われるだろうが)。
そして、人はなぜ結婚するのか、したいからするのか、更には、みな同じような理由でするのか、そこに経済的状況の違いは関係しているのか、人種的な違いはあるのか、男女で違いはあるのか——そういったことを、再考する必要があるということ。
また同時に、この映画には1点だけ不満もある。それは、経済的に余裕がないことを「クィア」なことと結びつけ、余裕があることを「普通」の側に結びつけていることだ。「わたしはお金あるけど考え方はクィアです」とか言う人たちのことはどうでもいい。経済的余裕がない人で、同性婚などの主流な運動を信じて協力したり、なけなしの金を寄付したりするクィアがいるということを、少しでもいいから描いて欲しかったと思う。
貧困層にも「『普通』の結婚がしたい」と思う人はいるし、その中にはクィアがいる。「いつか路上を出て『普通』の屋根がある『普通』のアパートに住みたい」と願うクィアがいる。「普通になりたい」「普通でありたい」という思いの危険性は、映画でも、この映画評でも十分に示されている。だからこそ、そういう思いに込められた葛藤や悲哀についても、深く掘り下げて欲しかったと思ってしまう。ルーカスの最後の言葉に、もしかしたらそういう悲哀が込められているのかもしれないと思えるからこそ、余計に。
マサキチトセ